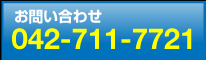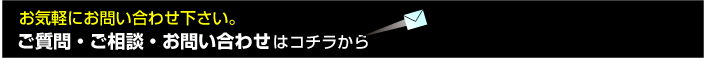ロストワックスの鋳砂除去
超音波鋳砂除去の対象は、自動車のエンジンブロックなどのアルミの鋳造品が主体でしたが、超音波の強化開発成功に伴い、FCDの鋳造品の一部でも 使用されるようになりました。
ロストワックスの鋳砂除去の多くは、湿式のショットブラストが使われているのですが、複雑な形状になればなるほど、効率が悪くなり、取り残しも増えます。そこで お客様からの依頼で、ロストワックスの鋳砂除去にも 超音波が使えないか 実験を始めました。
除去については、非常に良い結果なので、様々なロストワックスメーカーに呼び掛けて、超音波鋳砂除去を ロストワックス業界にも 広げることが出来るか、実験を推進する予定です。ロストワックスメーカーの皆さん。サンプルの提供をお願いいたします。
射出成型用ガラス製品の バリ取り技術
射出成型で ガラスを精密成型する。その場合、金型バリが発生するが、それは、超音波で、大部分を除去することが出来る。バリの根元にわずかに残ったバリは、同時に共用する治具の超音波強振動で除去される。角のR加工も同時に行うことが出来る。
1個2分程度かかるが、時計のカバーガラスレベルの大きさであれば、同時に100個~500個程度処理できるので 量産性に問題はない。
射出成型ガラスのバリ取りにも 超音波バリ取り技術は 有効である。
4トン 大型金型の強力超音波洗浄を標準化へ
金型洗浄依頼が増える中、1トンから、数トンの大きさの金型の丸洗い精密洗浄の依頼が増えている。
大きさ 幅1~2m。長さ1.5m~3m。高さ200mm~400mm 重さ1ton~5ton
当社は、洗浄、バリ取りの 1~7mの対象物を 大型の投げ込み超音波振動板を移動することにより、対応している。振動板は、洗浄対象物の底面を移動する場合、側面を移動する場合、対抗振動板が、側面を同期しながら移動する場合、対象物の上面を移動する場合など、様々な方法を 目的に合わせて 設計している。大型金型の場合は、重さ対策で、振動版が、金型上部を移動する方式であり、現在標準化を 進めている。
精密プローブ針のバリ取りについて
最近、超LSI 検査用のプローブガードに使用すると思われるプローブ針のバリ取り依頼が 増加している。 0.15mmφから様々で 中空の細管の端面のバリ取りも行う。非常に小さく細いので、水に浮いて流れて行ってしまうため、密閉容器中に プローブ針を入れて、超音波バリ取り実験を行う。この技術は、医療用の微小精密加工品のバリ取りで 開発された方法である。まだ、プローブ針のバリ取りに 課題をお持ちのお客様は、ぜひ、超音波バリ取り装置で、その性能をご確認いただきたい。
日刊工業新聞社発刊 プレス技術に 連載開始
超音波バリ取り 超音波洗浄の基本から 最新の応用技術までを 日刊工業新聞社の技術雑誌・プレス技術に 4回に分けて連載を開始いたしました。この間、国内外におけるセミナー、技術論文投稿などは、控えてきたのですが、お客様の要望に押され、新しい技術が次々に生まれ、超音波キャビティーションの応用技術も エネルギー効率を求める加工技術として 大きく進化し変わろうとしています。
当社は 機械販売メーカーなので 公開できる情報は 限られてはいるのですが、それでも この世界に関わりのある皆様に刺激を届ける事は出来ると思います。事業の足元を固めながら、様々な方法で 超音波キャビティーション応用技術の情報を発信していきます。
バリ取り比較一覧表
バリ取りにはたくさんの方法がありますが、それぞれ、メリットやデメリットがあります。
ワークに合ったバリ取り方法を選ぶことが大切です。
ぜひこのバリ取り比較一覧表をご覧ください。
超音波バリ取りの優位性がご理解いただけるはずです。